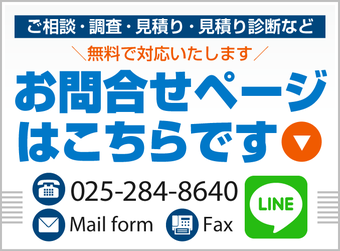自動火災報知設備の受信機は、自動火災報知設備の心臓部であり、火災時には何処で火災が発生したのかを表示し、スイッチ操作によりベルを止めたり、鳴らしたりすることもできる機械です。万一火災が発生した場合、受信機で場所を確認し初期消火に向かいます。防火管理者様に限らず予め受信機が何処にあるのか、どのように建物内が区分けされているのか?というのは防災上覚えておきたいポイントです。
新潟市西区事務所内にある受信機の交換工事を実施しました。この度の故障の原因は、40年以上経過しているので経年劣化により、受信機内部の基板故障が原因でした。基板故障は万一火災が発生した場合でも受信機表示されなかったり、非常ベルが鳴らなかったりするので重大な欠陥となっております。
受信機は自動火災報知設備の心臓部である為、全ての配線が集結します。まずは全てのケーブルの行き先を調べ、古い受信機から取り外しても行方不明にならないように記しておきます。
この作業を怠ると後々大変なことになってしまうので慎重に作業を行います。(慣れた作業ですが、1本・1本行き先を確認しメモを取って行きます)
今回の工事は、発信機、表示灯、地区ベルの交換もあるので、こちらも行方不明にならないように慎重に取替作業を行います。発信機、表示灯、地区ベルが収納されている機器収容箱ごと取り換えれば良かったのですが、鉄筋コンクリートに埋込ボックスが入っているので既設の収容箱を活かして中身を取り換えました。
息の合った二人での分担作業をしたので順調に進捗し交換作業は終了です。
今回はP型2級の受信機でしたので少しの設定をしてから動作試験となります。
(P型1級受信機になると設定箇所も増えるのでもう少し時間が掛かります。)
各感知器を作動させて、警戒区域番号の間違えがないか?ベルが鳴動するか?発信機を押したら蓄積機能が解除され火災断定になり、すぐ非常ベルが鳴動するか?などなど、細かいところまで試験調整をして完了です。
自動火災報知設備の火災受信機交換工事は、工事完了後速やかに試験結果を消防署へ届け出なければならない義務があります。試験も無事終了し帰社後届出書類を作成し提出して参りました。
今回はお客様の御協力もあり、故障を発見してから取替工事までの流れがとてもスムーズに出来ました。もし、故障した状態で火災があった場合、感知器も動作せず、非常ベルもならない状況では初期消火どころか避難することすら困難になってしまいます。
修理等を御検討されている方は是非当社へお早めにお声掛けを御願い致します。

今回はP型2級の受信機でしたので少しの設定をしてから動作試験となります。
(P型1級受信機になると設定箇所も増えるのでもう少し時間が掛かります。)
各感知器を作動させて、警戒区域番号の間違えがないか?ベルが鳴動するか?発信機を押したら蓄積機能が解除され火災断定になり、すぐ非常ベルが鳴動するか?などなど、細かいところまで試験調整をして完了です。
自動火災報知設備の火災受信機交換工事は、工事完了後速やかに試験結果を消防署へ届け出なければならない義務があります。試験も無事終了し帰社後届出書類を作成し提出して参りました。
今回はお客様の御協力もあり、故障を発見してから取替工事までの流れがとてもスムーズに出来ました。もし、故障した状態で火災があった場合、感知器も動作せず、非常ベルもならない状況では初期消火どころか避難することすら困難になってしまいます。
修理等を御検討されている方は是非当社へお早めにお声掛けを御願い致します。