はじめに
自動火災報知設備は建物を守る大切な砦です。しかし、ときには「誤報」という形で現場を混乱させることがあります。特に原因が明確でない場合、防火管理者さまは大きな不安を抱くはずです。本記事では、弊社が実際に対応した落雷による誤報事例を交えつつ、防火管理者さまが知りたい5つの疑問とそのアドバイスを整理しました。

事例概要と現場の様子
2024年9月、ある住宅型有料老人ホームで火災受信機が「警戒№4:2階天井裏」を発報しました。建物は2018年開所の延床770㎡超、当初から弊社が定期点検を担当してきました。設備は、自動火災報知設備、消防機関通報設備、水道直結式スプリンクラー、誘導灯、消火器を備えています。
防火管理者さまから通報を受け、弊社スタッフが急行。館内はすでにベル停止や電気錠の開放が行われ、消防署員も到着していました。現場の天井裏には煙も火の手もなく、同時に消防署員から「付近で落雷が確認された」との情報が寄せられました。
-
令和2年9月 落雷 → 受信機と感知器を全数交換
-
令和4年9月 落雷 → 煙感知器を全数交換
-
令和6年9月 落雷 → 特定エリアの感知器を交換
-
令和7年9月 今回の誤報
調査の結果、発報感知器の基板・光学部に目視異常はなし。しかし、雷によるサージ(瞬間的過電圧)が電子部品を損傷している可能性は拭えません。メーカー協力により無償で新品感知器を入手し、交換を実施しました。

防火管理者さまが知りたい5つのことと対応のアドバイス
1. 誤報時の初動対応

火災か誤報かをどう迅速に判断すべきか。消防署や業者への連絡はどの順番で行うべきか。多くの防火管理者さまが抱く疑問です。
アドバイス:
-
まず火災受信機で発報箇所を確認 → 現場へ直行し、煙・炎の有無を確認。
-
火災の可能性が少しでもあれば即座に消防署へ。誤報の可能性が高ければ業者に早急に連絡。
-
フローチャート化し、職員全員が共有・訓練しておくことで混乱を防止。
2. 原因が不明確な場合の扱い方
感知器の欠陥か落雷など外的要因か判断できないケースは多いです。どの時点で「交換」と判断すべきか、防火管理者さまにとって重要です。
アドバイス:
-
繰り返し誤報を出した感知器は、外観異常がなくても交換推奨。
-
落雷履歴がある場合、点検で異常がなくても「予防交換」の考え方が安全です。
-
判断基準を施設ごとに設定し、「曖昧だから様子を見る」ではなく「安全側で判断する」姿勢を持つことが大切です。
3. 過去の誤報履歴の活かし方
誤報が繰り返されるとき、履歴をどう管理・分析し改善につなげるか。
アドバイス:
-
発報日時・場所・原因推定・対応を必ず記録し一覧化。
-
傾向を分析し「季節要因」「特定エリアの弱点」を把握。
-
業者へ履歴を共有すれば、調査の精度や改善提案が向上。
-
管理者交代時の引き継ぎにも役立ちます。
4. 入居者や職員への説明方法
誤報発生時に入居者や職員の不安を最小限にする方法を知りたいという声。特に高齢者施設では重要です。
アドバイス:
-
事実を簡潔に伝える:「火災ではありません。設備の誤作動です」
-
安心感を与える:「現在業者が調査中、安全は確保されています」
-
職員向けには対応手順をマニュアル化し、誤報時でも冷静に動けるよう周知・訓練。

5. 再発防止のための具体的な対策
避雷針やサージ保護、感知器交換基準など「次に安心できる方法」を求める声。
アドバイス:
-
雷被害が多い地域は避雷針やサージ保護装置の設置を検討。
-
落雷発生後の臨時点検をルール化し、潜在故障を早期に発見。
-
感知器は10年を目安に更新、誤報が繰り返される場合は早期交換を。
-
「誤報も学び」として改善サイクルに取り込むことが施設全体の安心につながります。
まとめ
今回の事例では、感知器の欠陥か落雷の影響か原因を特定できませんでした。しかし、防火管理者さまにとって重要なのは「誤報が起きた際の行動」です。誤報を軽視せず記録・分析し、業者と協力して改善につなげることで入居者の安全を守ることができます。
自動火災報知設備は敏感であってこそ命を守ります。誤報もまた「安全を知らせるサイン」と捉え、防火管理者さまと私たちが共に備えることで、確かな安心を築いていきましょう。
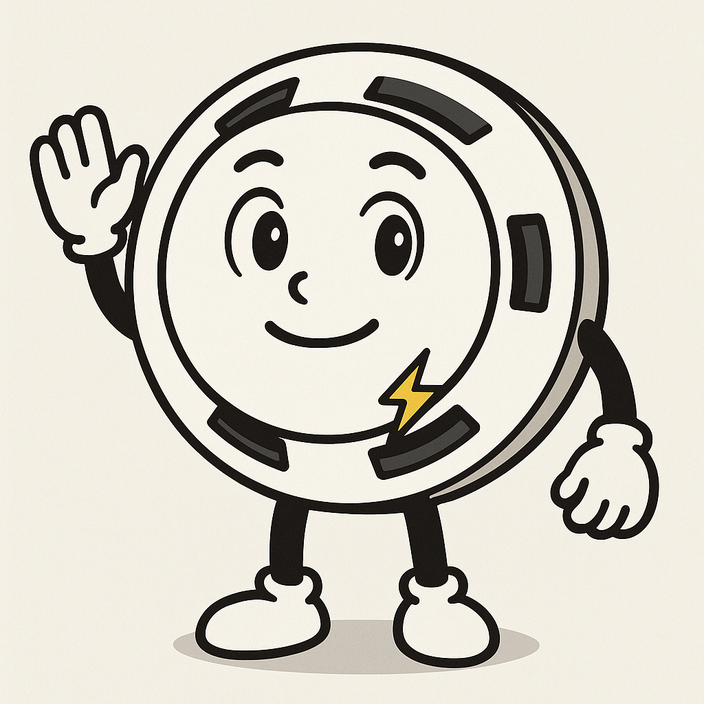
✦ 自動火災報知設備研究所より ✦







